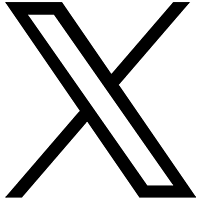大西暢夫プロフィール
1968年生まれ。岐阜県池田町出身。
東京綜合写真専門学校を卒業し、写真家・映画監督の本橋成一氏に師事。
29歳で独立。その後、フリーカメラマンに。
日本最大のダム建設に翻弄される岐阜県徳山村をはじめ、全国各地のダムに沈む村の取材を同時に始める。ほかに精神科病棟に長期入院する患者さんや、東日本大震災、障害者施設や職人など、根底には、『衣食住』をテーマにしている。そのほかにもドキュメンタリー映画も制作している。
2025年日本写真協会賞受賞。現在は、雑誌連載、映画制作、執筆など。

主な著書
『僕の村の宝物』(情報センター出版局)1998年
『分校の子どもたち』(カタログハウス)2000年
『山里にダムがくる』(山と渓谷社)2000年
『おばあちゃんは木になった』(ポプラ社)2002年 第8回日本絵本賞・全国学校図書館協議会選定図書
『ひとりひとりの人~僕が撮った精神科病棟~』(精神看護出版)2004年全国学校図書館協議会選定図書
『花はどこから』(福音館書店)2005年
『水になった村』(情報センター出版局)2008年
『徳山村に生きる』(農文協)2009年
『アウトサイダー・アートの作家たち』(角川学芸出版)2010年
『ぶた にく』(幻冬社)2010年 第58回産経児童出版文化賞大賞・第59回小学館児童出版文化賞
『糸に染まる季節』(岩崎書店)2010年
『東北沿岸600 キロ震災報告』(自費出版:岐阜新聞社協力)2011年
『3.11 の証言』(自費出版:岐阜新聞社協力)2012年
『ミツバチとともに』(農文協)2012年
『津波の夜に』(小学館)2013年 全国学校図書館協議会選定図書
『シイタケとともに』(農文協)2015年 2023年 岩手県課題図書
『ここで土になる』(アリス館)2015年 2016年 全国課題図書
『ホハレ峠』(彩流社)2020年 第36回農業ジャーナリスト賞
『お蚕さんから糸と綿と』(アリス館)2020年 2021年 福島県/ 新潟県/ 鳥取県課題図書
『和ろうそくはつなぐ』(アリス館)2022年 2025年JBBY選定図書
『ひき石と24 丁の豆腐』(アリス館)2024年 2025年 第72回産経児童出版文化賞大賞 2025 年 岩手県課題図書
『炎はつなぐ』(毎日新聞出版)2025年 6月出版
『やさしいカタチ』(彩流社)2025年7月発売
映画監督作品
『水になった村』2007年
『家族の軌跡』2015年
『オキナワへいこう』2018年
『炎はつなぐ』2025年7月19日より公開予定